メンタル不調を抱えていると、仕事の選び方、日々の気分の波、家族や周囲との関係など、様々な悩みにぶつかられると思います。「復職はまだ無理かもしれない…」「どうすれば自信を持てるのだろう…」そんな風に感じることもあるのではないでしょうか。
昨年(2024年)11月、リヴァトレ大阪本町で開催されたイベントでは、精神科医の益田裕介先生と弊社取締役 青木弘達が、参加者の方々から寄せられたリアルな質問に答えるQ&Aセッションが行われました。
本記事では、そのQ&Aセッションから「働き方や収入のバランス」「社会復帰への不安」「自己肯定感の悩み」「復職後の不調」「家族との関わり方」といった疑問に対する、考え方のヒントを抜粋してご紹介します。
防衛医大卒。防衛医大病院、自衛隊中央病院、自衛隊仙台病院(復職センター兼務)、埼玉県立精神神経医療センター、薫風会山田病院などを経て、早稲田メンタルクリニックを開業。
益田先生のYouTubeチャンネル「精神科医がこころの病気を解説するCh」
目次
収入と無理のない働き方
どっちを選ぶべき?
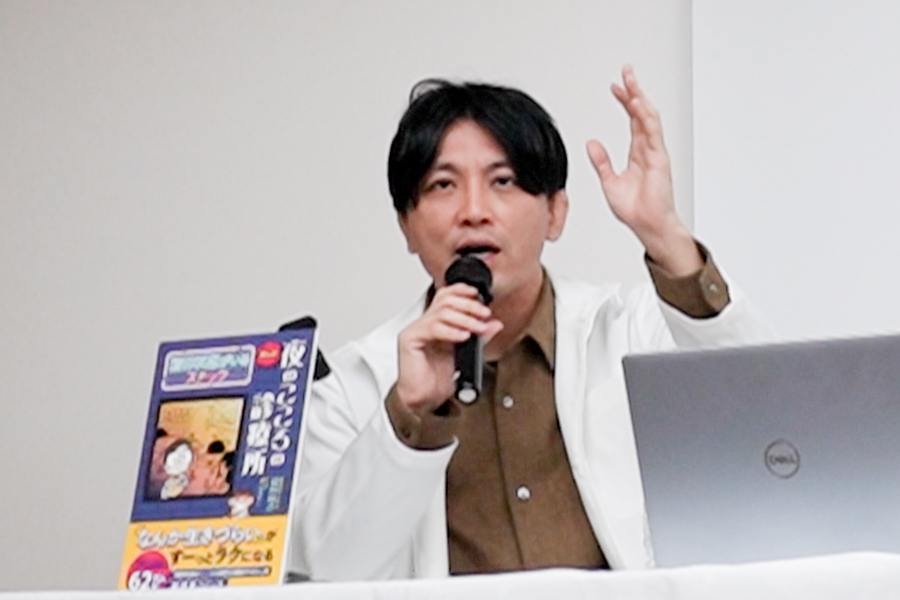
益田先生:診察の現場でも、まずは自分のメンタル疾患を認めたうえで、できるだけ高収入で負担の少ない仕事を探すべきだという話になることが多いですね。メンタル疾患を隠して働くのは、現実的には難しい場合がほとんどです。だからこそ、疾患を認め、自分に合った働き方を探していく必要があります。
最初は思うようにいかず、適した仕事が見つからないこともあるかもしれませんが、市場は年々変化しています。少しずつ状況を見極めながら、転職のチャンスを待つのも一つの方法ですね。
青木:そうですね。私自身は少し違うケースですが、日光アレルギーがあるんです。外で活動するときは長袖や日焼け止めが必須ですし、昼間の外出には大きな制限があります。もし自分の特性を無視して行動し続けたら、最終的には身体がもたなくなってしまう。
困りごとの種類は違っても、メンタル不調も同じように考えられると思います。自分の特性を認め、受け入れたうえで、そのなかでどこまで頑張れるかを考える。ただし、無理をしすぎるのはおすすめできません。誰だって無制限に頑張り続ければ倒れてしまいますから。
結局は、自分をよく理解し、小さな一歩を積み重ねることが大事なんだと思います。先ほど益田先生もおっしゃっていましたが、環境や状況は時間とともに変化します。その変化に柔軟に対応しながら、できることを積み重ねていくと、自然と自分に合った働き方が見えてくるのではないでしょうか。
「この状態で働ける?」
うつ病から社会復帰への不安
質問②:うつ病を抱えながら社会復帰を目指していますが、気分の落ち込みがひどい時には消えたくなることもあり、日常生活を送るのも難しい状態です。このような状況ではまだ社会復帰はできないかもしれないと感じています。
うつ病患者の社会復帰とはどのようなものでしょうか?また、障害者枠で働くことになるのでしょうか?どんな仕事が向いているのか教えていただけますか?
益田先生:最近の研究では、うつ病は脳の炎症反応が原因だと言われています。これを植物の「根っこ」に例えると理解しやすいのですが、植物の根を引き抜くと、細かい根が土をつかんでいて、目に見えないほど細い部分もありますよね。それがストレスなどで切れてしまった状態が、「うつ病」なんです。
この状態を治すには、時間をかけてゆっくりと根を育てる必要があります。植え替えたばかりの植物がすぐに大きくならないのと同じで、うつ病の社会復帰もゆっくり時間をかけていくもの。最初は見た目の変化がなくても、数年たつと急に伸びることがあります。これが、うつ病の回復と同じイメージです。
年齢による差もあります。10代や20代は回復力が高い一方、50代になると治りづらくなる傾向がある。また、回復のペースも個人差があります。
ある人は根がしっかり伸びるけれど、別の人は土壌の状態が悪かったり、幹や葉っぱが弱っていたりして回復が進まないこともあります。一度伸びたように見えても、環境の変化やストレスで再びダメージを受けてしまうケースもあるんです。
表面的には元気そうでも、根っこが十分育っていないこともある。その段階で無理をしてしまうと、かえって回復が遅れてしまいます。
青木:分かりやすいですね。私からは別の角度からお伝えをすると、「社会復帰しなきゃ!」と思い詰めている時期は、実はまだそのタイミングじゃないことが多いです。焦って動くとうまくいかないんですよね。
薬が効いて少し落ち着き、「この生活をもう少し続けたいな」と思えるくらいが、案外社会復帰のタイミングだったりします。また、障害者雇用で働くのが良いかどうかは、その人の特性によると思います。メンタル不調だからといって障害者雇用が必ずしも合うとは限りませんし、逆に負担が増える場合もあるんです。
だからこそ自分の特性を理解し、自分に合う環境を見極めること。焦らず、合った働き方を探すのが大切だと思います。就労移行やリワークを通じてインターンシップに参加するのも一つの方法ですね。頭で考えてもわからないことが、実際に体験すると見えてくることも多いです。
それから、もし「早く社会復帰しなきゃ」と焦っているのであれば、まだ十分休養が必要な時期なのかもしれませんね。社会復帰を目指す気持ちも大切ですが、まずは自分の身体と心の声を聞きながら、少しずつステップを踏むことをおすすめします。

「自分はダメだ」と感じてしまう…
自己肯定感の育て方とは?
益田先生:僕がよくお伝えしているのは、「仕方がない」と思うことの大切さ、そして「生まれてきてよかった」と思える瞬間を増やすことです。自分に劣っている部分があるのは仕方がない。そのうえで、じゃあどうするのか。
例えば、僕自身、ほかの医師やYouTuberと比較してしまうことがありますが、医師免許があるおかげで必要とされる場が必ずあるんです。これは医師だから特別というわけではなく、どんな人にも「必要とされる場所や役割」はあって、あなたを求めてくれる人はいます。
質問者さんは「自分を知るほど、自己肯定感が下がる」とおっしゃっていますが、これ以上掘り下げなくてもいいと思っていて。むしろ「自分がどこで求められているか」を知りに行くほうが大事なんです。
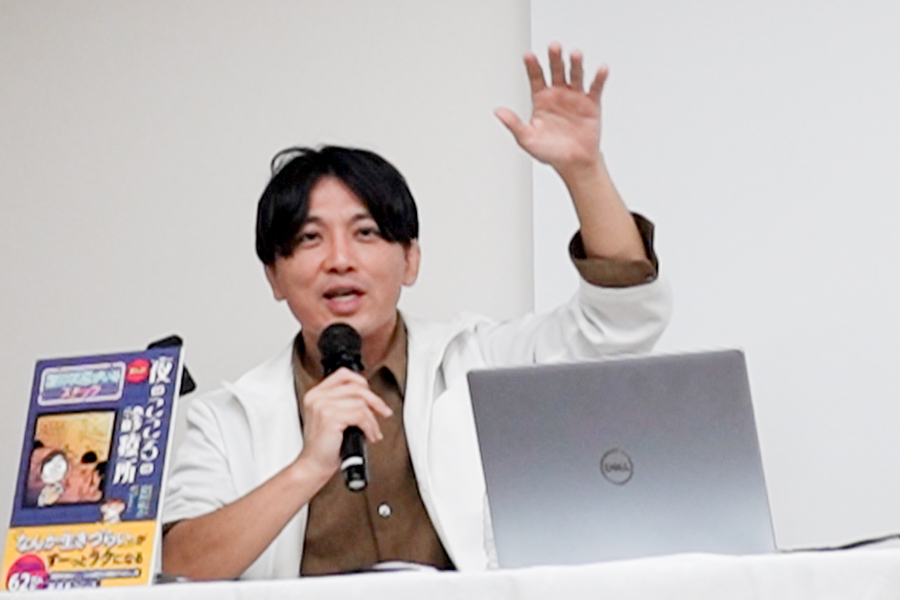
青木:人間の脳は悪い情報を拾いやすい性質があって、昔はそれが生き延びるために必要だったんですが、現代ではストレスの要因になっています。だからこそ、意識的に「良かったこと」や「少しマシだったこと」を見つける練習をするのが大切です。
たとえば、「今日はコンビニで買ったお菓子がおいしかった」くらいの小さなことで大丈夫です。そうした小さなポジティブ要素を書き留めるだけでも脳にはいい刺激になります。
今の時代、情報が多すぎて「もっとすごい人にならなきゃ」と思い込みがちですが、実際にはそんな必要はありません。先生がおっしゃったように「仕方がない」と受け入れる姿勢を持つことで、自分という存在が少しずつ見えてくるはずです。
ないものを数えればキリがありませんが、あるものに目を向けると驚くほど多くの良いことに気づけるもの。「どこに目を向けるか」が、自己肯定感を高める大きなカギだと感じます。
復職しても続く、心身の不調。
回復のイメージが持てない時、どうすれば?
質問④:重度のうつ病で2年間休職し、休職期間が満了したため復職しました。休職中はリワークに通い続け、復職から1年になりますが、遅刻や欠勤が続いています。どうしたら良くなるのでしょうか?
益田先生:重度のうつ病は、いわゆる通常のうつ病とはまた違う面があります。早期に休養を取って回復する方もいれば、閉鎖病棟で数ヶ月から1年近く入院しながら回復を目指す人も。
そして残酷ではありますが、ご本人の努力や意志だけでは、どうしても変えられない現実や限界というものは存在します。私が日頃から「仕方がない」と思うことの大切さをお伝えしているのは、そうした自分の力ではどうにもならない現実と向き合う上で、それが重要な考え方の一つになるからです。
青木:質問者の方は「良くなるイメージが持てない」とおっしゃっていますが、「良くならなければならない」という思いに縛られすぎているのかもしれません。重度のうつ病を抱えながら復職し、遅刻や欠勤があるとはいえ仕事を続けられているというのは、それだけでもすごいことだと思うんです。
晴れの日や雨の日があるように、体調も良い日と悪い日がありますよね。一番しんどかった頃と比べて、今の状況はどうでしょう?
振り返ってみると、案外頑張れていると気づくこともあるかもしれません。その進歩に目を向けるだけでも、「自分、頑張ってるじゃん」と思えることもあると思います。理想の状態と比べると苦しくなる場合もありますが、その比較がモチベーションになるならいいものの、プレッシャーに感じるようなら、過去の一番辛かった時期と比べて「ここまで良くなってきた」と実感する視点も大切です。
私たちが支援するなかでも、「こうあるべき」という価値観や周囲のプレッシャーが、回復を妨げるケースをよく見ます。そんなときは、自分のなかで少し視点を変えてみるのが大事ですね。「今日はこれだけできた」と自分を肯定する習慣を持つことで、その積み重ねが状況を少しずつ好転させるかもしれません。

パートナーが双極性障害。
仕事やお金のトラブルに対して、どう関わればいい?
益田先生:非常に難しい問題ですが、まず治療については主治医にしっかり任せることが大切です。奥さんが治療者のような役割になると、家族としての立場と治療者としての立場が混在してしまい、関係が混乱してしまいます。
また、お金の管理に関しては、感情的に「あなたはだらしないから私が管理する」と言うのではなく、病気の特性で判断が難しくなるときがあることを理解したうえで、「夫婦で公正なルールを作ろう」という形にしたほうがスムーズだと思います。
たとえば、「◯円以下の買い物は本人の裁量でOK、◯円以上は夫婦で合意する」といった、具体的で分かりやすいルールがあるといいですね。そして、冷静な状態のときに最終的な決定権をどうするかも含めて話し合っておきましょう。
躁(そう)の状態になると判断力が高まり、口が立つケースも多いので、言い負かされてしまうことがあるんですよね。そうしたリスクを最小限に抑えるために、あらかじめルール化しておくことが重要です。
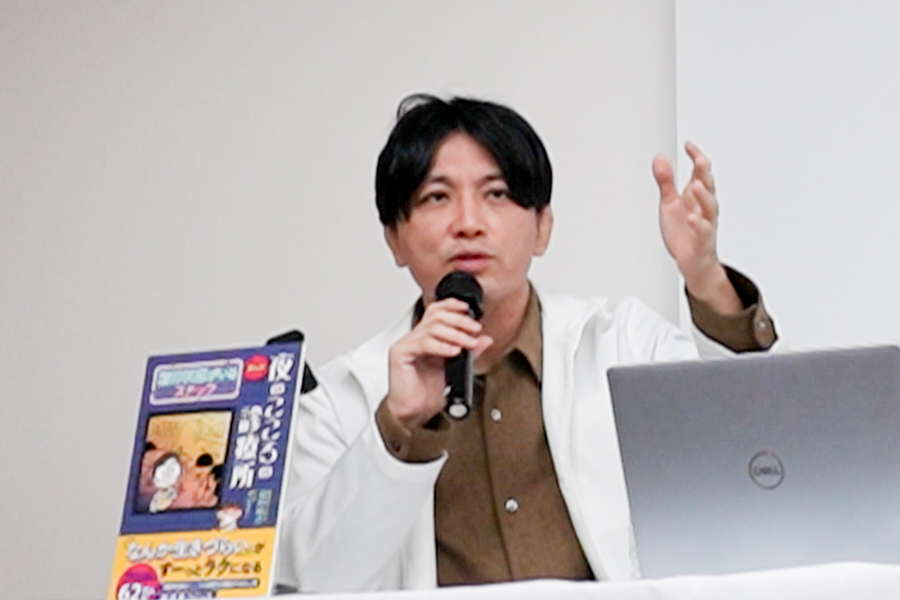
青木:奥さんとしては、ご主人と向き合うのが本当に大変だと思います。治療面では主治医や専門家との連携が不可欠ですが、家族カウンセリングや当事者会を活用するのもよい方法ではないでしょうか。
1対1で話し合うと感情的になりやすいので、第三者を交えたほうが冷静に話せることが多いです。「家族の状態をより良くしたいから、カウンセリングに行ってみない?」といった前向きな誘い方なら、ご主人も受け入れやすくなるかもしれません。
さらに、家族カウンセリングでは「誰が悪いか」ではなく、「家族全体としてどう良くしていくか」を目的に話し合えます。同じような悩みを持つ人が集まる家族会や当事者会も、奥さん自身が抱える負担を軽減する役に立つと思うので、そうした社会資源を積極的に活用してみてください。
本記事でご紹介した内容の全編は、以下のYouTube動画でご覧いただけます。
まずは無料パンフレットをご覧ください
リヴァトレは、うつなどのメンタル不調でお悩みの方の復職・再就職をサポートするリワークサービスです。
復帰に向けて行う取り組みについて、無料パンフレットでわかりやすくご紹介しています。
まずはお気軽にお申込みください。
※実際の支援スタッフへのご相談、事業所のご見学はこちらから
LINE公式アカウントでメンタル不調からの回復に役立つ限定情報配信中!
リヴァトレのLINE公式アカウントでは、現在休職・離職されている方に向けて、月に数回ほど登録者限定の情報を発信しています。
- LINE登録者限定Youtube動画「脱うつに役立つプログラム『CBGTメンテナンス』をやってみよう」をプレゼント中
- リヴァトレ主催のイベントをご案内
- メンタル不調からの回復に役立つ情報発信
少しでもご興味がある方は、ぜひ下記バナーをクリックして友だち追加してくださいね。





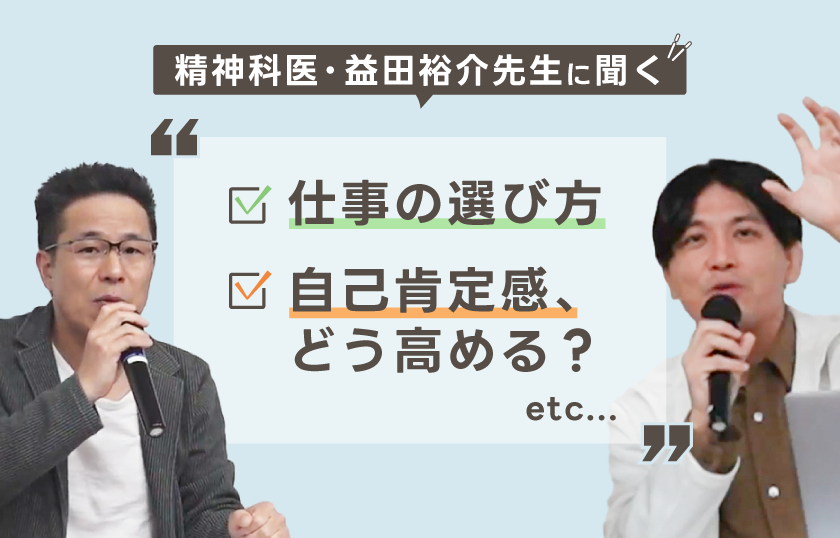
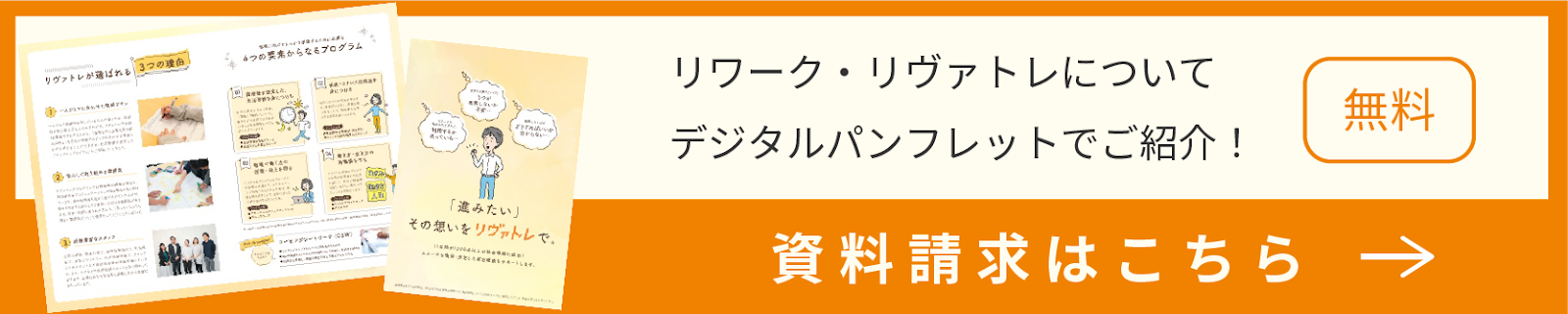



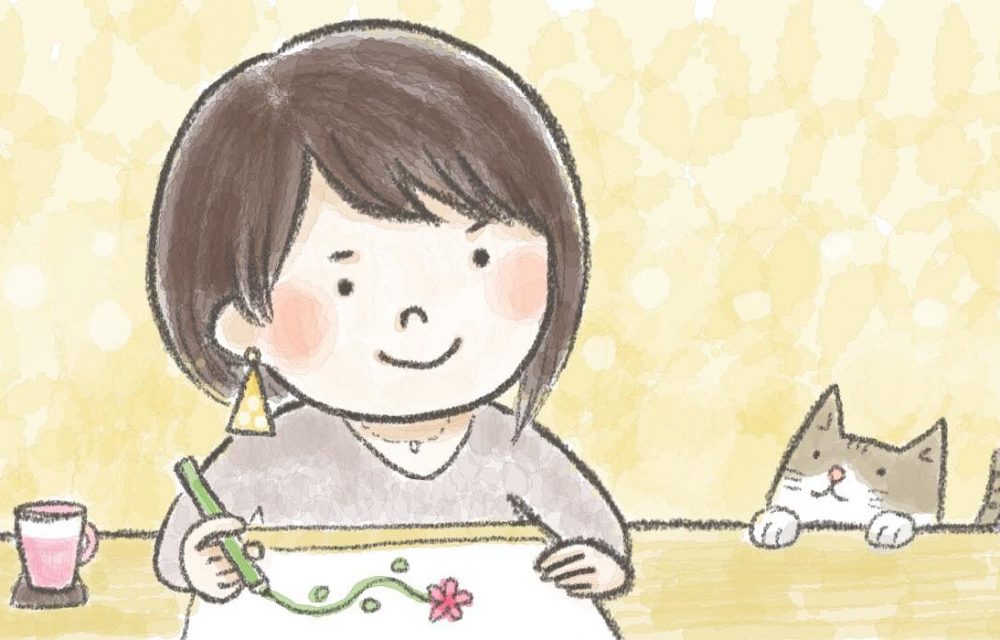



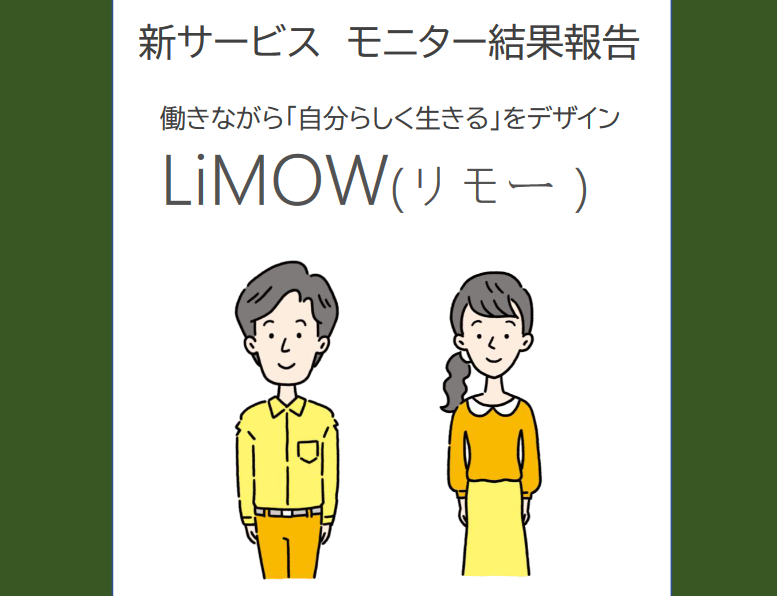






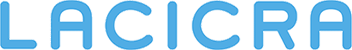
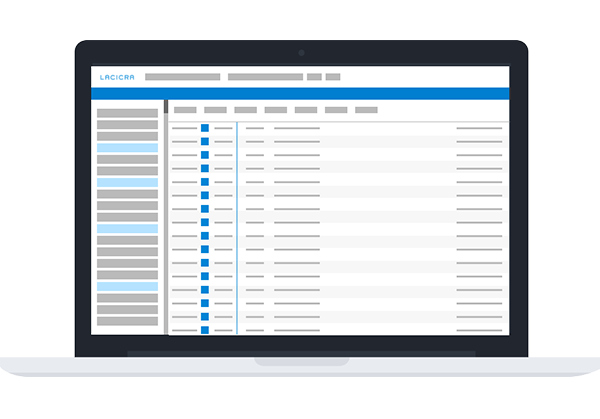

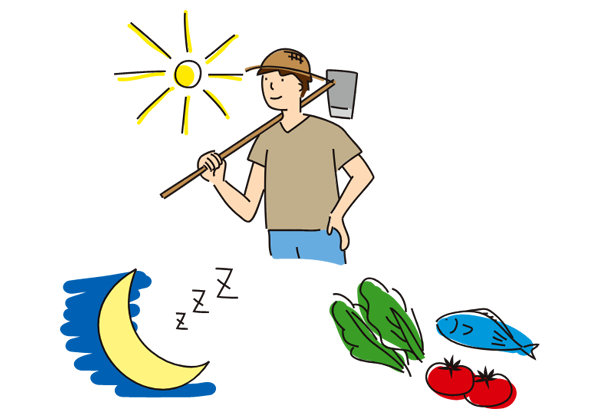
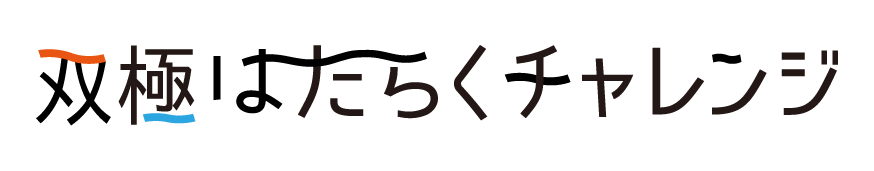
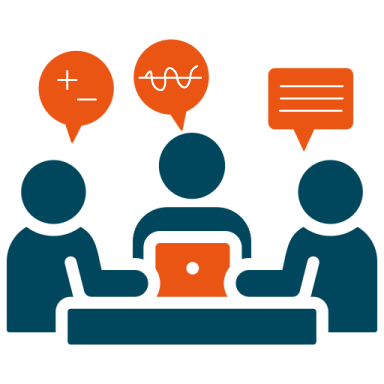
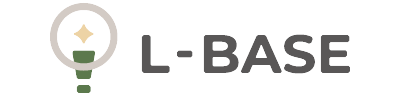
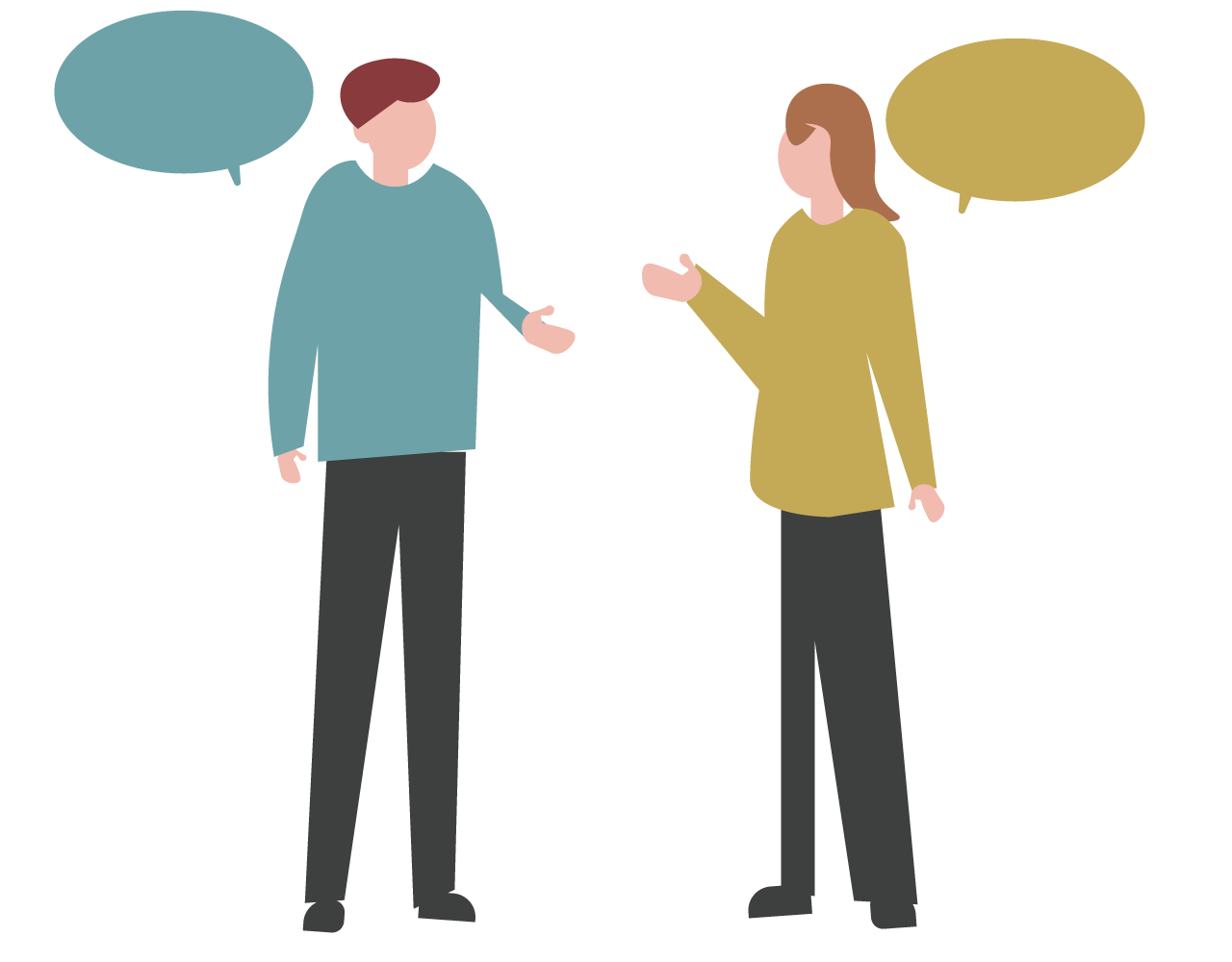

1996年福島県生まれ。山形大学を卒業後、18卒として(株)リヴァへ入社。ラシクラ事業部・新卒採用の責任者を兼任しながら、新規事業「あそびの大学」の立ち上げに至る。自分らしいと感じる瞬間は「物事の背景を探求している時」。趣味は、DIYと金継ぎ。